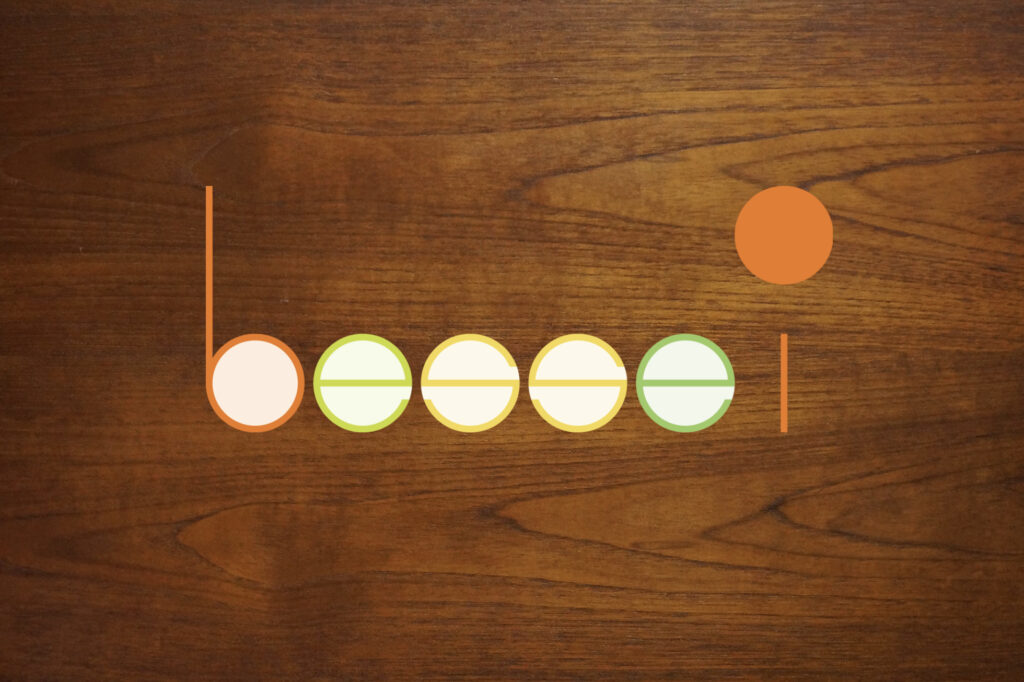代表 福沢恵子

私が新聞記者として夫婦別姓を求める動きを取材したのは20代の終わりでした。あれから30年余りの歳月が経過しても、日本ではまだ夫婦がそれぞれ生来の苗字のままで法律婚ができません。
家族のあり方は多様化しています。夫婦に同姓を強制することで、この国はどれほどのものを失ったのでしょうか。結婚を忌避する若い世代、ますます加速化する少子化。これは現在の結婚のあり方があまりに窮屈であることの反映ではないかと思います。今回の訴訟はこの閉塞した状況に風穴を開けるものです。勇気を出して立ち上がってくださった原告の皆さんを弁護団と共に支えて参りたいと思います。どうぞご理解・ご支援のほどよろしくお願いいたします。
副代表 小国香織

2015年に最高裁で判決が出された第1次(選択的)夫婦別姓訴訟で原告となり、第2次、そして今回の第3次訴訟では支える会で応援に回っています。「自分の名前の事は自分で決める」ーーささやかながらも大事な尊厳が、今の日本の法律では結婚というつながりと引き換えにされています。ある知り合いのアメリカ人で、私が第1次訴訟に関わっていたと英語圏のメディアを通して知ってくれた人から「政府の名前じゃない、『私』の名前だよね」と言われて、その言葉通りのシンプルな課題だよね、と思っています。シンプルな課題ながら司法での闘いには難しい論理が必要ですが、そこは頼もしい原告団・弁護団の皆さんに託すしかありません。その分、皆さんのご注目、ご協力が力になります。よろしくお願いします。
メンバー 上田めぐみ
-edited-1.jpg)
第2次別姓訴訟から支える会事務局メンバーとして活動してきましたが、第3次訴訟には原告と事務局の「二刀流」で挑みます。
弁護団が作成する訴状や書証はとても説得力のあるものです。でもこの裁判はこれだけでは足りません。社会や世論は大きく変化していて、結婚の際に、別姓も同姓も選べる法改正を待っている人たちがたくさんいることを司法に理解してもらう必要があります。そのために、みなさんに声を上げてほしいのです。
第2次訴訟開始時に比べて、SNSや動画がもっと身近になりました。あらゆる層にアプローチできるよう、第3次訴訟ではメンバーの総力を結集し、SNSや動画配信を充実させて裁判の情報をお伝えしていきます。
全力で頑張りますので、拡散とご支援をお願いします。
メンバー 恩地 いづみ

二次訴訟で広島の原告になったころ、「もう、流石に法律変わらんといかんやろ」と思っていました。けれども、最高裁まで終わっても未だ微動だにしていません。泣泣、です。
選択的夫婦別姓を求める思いは千差万別。100組のカップルに200の思いがあります。
原告の皆さんと支える会の私たちは、それぞれの思いを持ちつつ同姓強制の今の日本社会で感じている痛みを共有して、そこで繋がってこの社会を変えていきたいと力を合わせています。
今度こそ。一歩進ませましょう。
私たちに加わってください。支援をお願いします
メンバー 夕月(ゆづき)
東京都内で、事実婚の夫と二人の子どもを育てています。選択的夫婦別姓制度の実現のため、何か自分にできることをしたいと、いても立ってもいられなくなり、2018年秋から事務局メンバーとしてメルマガの作成などをしています。法改正の日まで頑張ります。
メンバー 高島紗綾
結婚当初から別姓の選択肢ができたら法律婚しようと思い、第2次(選択的)夫婦別姓訴訟では原告となりました。しかし、望んでいた違憲判決は得られず、別姓の選択肢のある制度は実現していません。
でも諦められません。自分の名前で、相手の意思を尊重し(相手に改姓を強制することなく)、法律婚することを。
同じように別姓の選択肢のある制度を求める人々が、原告として声をあげ、弁護団は全力で訴訟に臨んでいます。
別姓にしたい人のみならず、選択肢の中から同姓を選択したい人、将来結婚するかもしれない人も、傍聴に行ったり、寄付したり、関連記事を友人と話題にしたり、それぞれの方法で応援お願いします。